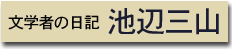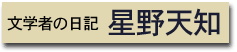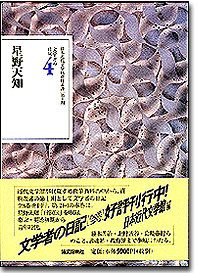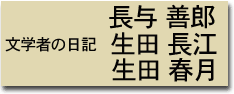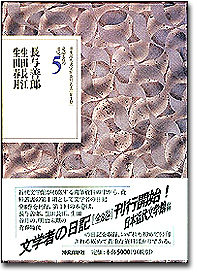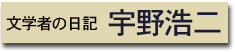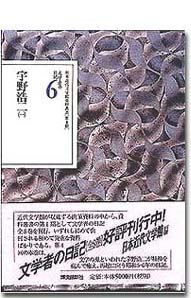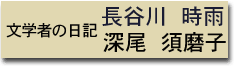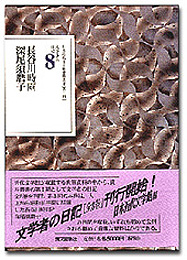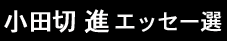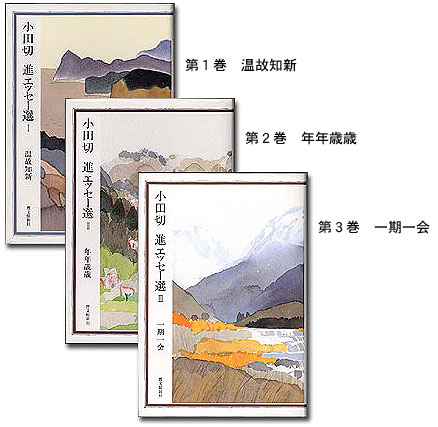博文館新社の叢書・全集
日本近代文学館資料叢書[第2期]
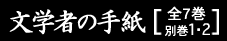
日本近代文学館編
文学者の手紙は、本来公表を予期することなく
書かれたものなので、彼らの肉声を聞くかのよう
な興趣に富み、また、創作の秘密を解く鍵を提供
している場合も多い。そういう意味で、文学者の
手紙はまことに貴重な文学資料であるが、解読、
解説は決して容易なことではないし、商業的出版
物として採算性もとりにくい性質のものである。
こうした困難を克服して、ここに『文学者の手
紙』が多くの関係者のご協力により刊行に至った
ことは、文学館の担う責務の一端を果たす意義ふ
かい事業であると確信している。
日本近代文学館理事長 中村稔「刊行のことば」
から |
文学館所蔵の膨大な書簡から、
未公表多数を含む貴重書簡を編集!
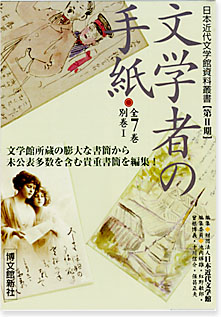
『文学者の手紙』リーフレット表紙 |
好評発売中
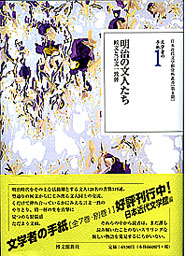 | |
十川伸介、笹瀬王子、松村友視、宗像和重、吉田昌志 編

A5判・上製カバー装 定価 6,930円(税込)
|
本巻には、明治時代をその主な活動期とする文人128名の書簡319通を収
める。慶応元年8月の福地桜痴の書簡から大正14年6月の内田魯庵の書簡まで、
その内容、文体は実にさまざまであり、特定の文学者の評伝や概説的な文学史か
らは得られない生々しい息吹を読者は感受することになろう。
編者5人による解説では、「候文と言文一致の角遂」「手紙が架橋する距離」
「佐佐木信綱宛書簡に見られる人と時代」「手紙の中の紅露逍鴎」「一葉宛書簡」
や漱石書簡が映し出す文学」などについて論じられる。本書の読みがいかに多様
でありうるかは、このことからも窺うことができるだろう。
型通りの候文からにじみ出る文人同士の交流、くだけて狎れ合っているかに見
える言文一致のやりとり、精一杯の生を真摯に見つめる緊張感ただよう文面。
それらの中から読者は、まだ誰も読み解いたことのないスリリングな物語を発見
するに違いない。
好評発売中!
中嶋歌子、渡邊澄子、尾形明子、岩淵宏子、吉川豊子、阿木津英 編
 A5判・上製カバー装 定価 6,930円(税込)
A5判・上製カバー装 定価 6,930円(税込)

明治から昭和まで46人292通の書簡で読む、愛と暮らしと表現の女性史。
田村俊子、柳原白蓮、岡本かの子、岡田嘉子、五島美代子・・・・その流麗な女
手は、誇りをもって自らの生を証しつつ、男になしがたい繊細な鋭さで時代を刻
印する。新たな発見に満ちた貴重な資料集。もはやこの一冊なしに近代文学は語
れない。
好評発売中!
 | |
曾根博義、安藤宏、佐藤健一、十重田裕一 編

A5判・上製カバー装 定価 6,930円(税込)
|
昭和の文学者たちの書簡にみえる精神の風景は、実に多様である。その多様の底に大き
く横たわっているものは、昭和の戦争である。中でも、芥川比呂志宛の中村真一郎・堀田
善衛の書簡からは、戦時下の時局とのかかわりに対照をみせながらも、そう生きねばなら
なかった若い芸術家の心中の叫びが響いてくる。一方、徳永直に宛てられたいわゆる左翼
作家たちの書簡からは、自己定立の苦渋がにじみだしている。
本巻では、川端康成・片岡鉄兵らの書簡を主とする「新感覚派作家たちとその周辺」、
深尾須磨子書簡と徳永直宛の諸作家の書簡を中心とする「昭和詩とプロレタリア文学運
動」、伊藤整・中村真一郎・堀田善衞書簡を中心とする「モダニズム文学の流れ」、さら
に若い五味康祐・水上勉・小田実たちの生まれ出ようとするエネルギーを感じさせる「著
者と編集者」の4つの章に分けて、313通を収める。
これらの書簡からは、文学史から忘れられたようにみえる、文学者一人ひとりの、その
時々の真摯な姿が生き生きとよみがえってくる。
 | |
長谷川啓、北川秋雄、小林裕子、中野武彦、満田郁夫 編

A5判・上製カバー装 定価 6,930円(税込)
|
佐多の書簡150通、来簡110数通を収録、3章で構成した。激動の時代を生き抜い
た作家・佐多稲子の人生を、一通一通が興味深く語りあかす。文学的価値はもとより、手
紙とは何よりもまず励ましであり、思いやりであり、けれんのない主張であることが理解
されるであろう。文学者から作品のモデルまで、多岐にわたる人物が登場する。とりわけ
中野重治・原泉との深い交流には、思想・運動・文学・生活のあらゆる面が反映され、互
いに、かけがえ
のない生涯の盟友であったことがここから改めて読みとれよう。徳永直、壷井栄、野上
弥生子、これらの人々とどのように心を通わせていたか、これまでの文学史ではうかがえ
ない証言と真実が、それぞれの書簡に潜んでいる。
「何の涙か分らない。あなたに会へるもう一度?・・・・・・生きていてもう一度会へ
るか何うか」(田村俊子の上海からの便り)。切々と心情を吐露するこんな文章に出会え
るのも、本書の大きな魅力の一つである。
 | |
池内輝雄、須田喜代次、日高昭二、柳沢孝子 編

A5判・上製カバー装 税込価格 6,930円
|
芥川を筆頭に吉江喬松まで、ほぼ90名、387通の書簡を収めた。文学・芸術・思想
に携わり、またそれを志した人々の、若々しい感性と知性が全編に横溢する。書簡という
形をとった短編作品群の、躍動するアンソロジーともいうべき1冊である。
モダニズム、大正デモクラシーのもと、思うがままに花開こうとする個性が、そこには
確かに存在した。時に他者に向かって真剣勝負をいどみ、高度の思索を展開し、深い懊悩
をぶっつける。書面に刻まれた個々の意識と営みがデジタルとバーチャルの現代が忘れ去
り、見失ったものを改めてよみがえらせてくれるだろう。モダンという言葉は、近代と現
代の生き生きとした両義性を有するものにほかならなかったのだ。
芥川に関する新発見もある。文壇の裏事情がほのみえて読む者の興味をそそる書簡も少
なくない。大正という短い期間にあえてくぎったことにより、時代を織りなす人々の構図
とその精神が、自ずからうかび上がってくるのも本巻の特長であろう。
 | |
保昌正夫、竹内栄美子、十重田裕一、宮内淳子 編

A5判・上製カバー装 税込価格 6,090円
|
昭和8年、高見順は転向後、同人雑誌「日暦」を創刊し、「故旧忘れ得べき」を発表し
た昭和10年には、生涯の伴侶となる秋子夫人との結婚生活を始めている。本巻に収めた
書簡は、この時期以降のものが中心となるのだが、それは高見順の仕事を支え続けた秋子
夫人の手によって書簡が丁寧に保存された結果である。本書では、その未発表の書簡を、
第1部「第1章 高見順から秋子へ」「第2章 秋子から高見順へ」、
第2部「第1章 高見順から知友へ」「第2章 知友から高見順へ」
という2部で構成した。
第1部のように夫婦間で手紙のやりとりがあったのは、高見がよく温泉地や避暑地で執
筆していたことの他に、徴用といった戦時の影響がある。またここには、「文士の妻の
鑑」と言われた秋子夫人が、人前では出さなかった愛情を夫に向けて語った書簡も入って
いる。
第2部では、「日暦」「人民文庫」「大正文学研究会」などの人々との交流の他、日本
近代文学館創設時のやりとりなど、文士・高見順のすがたが浮かび上がる。情に篤く面倒
見の良かった高見の性質や、彼が昭和文学史の中枢にいたことがよくわかる、貴重な資料
となろう。
|
開館当初より有島生馬、その娘の暁子より寄贈の有島3兄弟関係の手紙が大量にある。
彼らを軸にして編成。志賀直哉らのものも添える。
(1)有島武郎の手紙 武郎は上の資料を吸収した筑摩版全集が出ているが、家族宛(両
親、妻安子など)のものは、その筆跡も興味深く、留学中の絵葉書、スケッチ、療養中の
妻安子への、聖なる少女愛を示す写真を伴った手紙は影印で示し、実在感を抱かせる。
(2)武郎宛の手紙 札幌の遠友夜学校の生徒・瀬川すゑ(武郎による朱の書き入れあ
り)や早川三代治・吹田順助・足助素一ら武郎周辺の重要人物。さらに多くの武郎ファン
(読者)からの直接の作品をめぐっての反応を示すものが中心。
(3)生馬の手紙 生馬の全集には手紙は一切未収録。武郎宛の生馬の手紙を全面公開。
(4)生馬宛の手紙 その友情に屈折のあった志賀直哉の手紙は影印で示し、さらに竹久
夢二や「生まれ出る悩み」の木田金次郎、二科会以来の重要な画家の手紙。島崎藤村・佐
藤春夫・呉茂一・神西清・谷崎潤一郎・本多秋五・瀬沼茂樹らの手紙。森雅之も加える。
(5)里見の手紙 里見の全集には手紙は一切未収録。生馬宛の手紙を中心に全面公開。
実篤らの「白樺」主流との落差が確認できる。
| 
| 第1巻(7) |  | 十川信介、笹瀬王子、松村友視、宗像和重、吉田昌志 編 |
| 第2巻(2) | 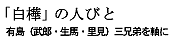 | 紅野敏郎、町田栄、山田俊治 編 |
| 第3巻(3) | 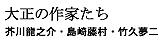 | 池内輝雄、須田喜代次、日高昭二、柳沢孝子 編 |
| 第4巻(6) |  | 曽根博義、安藤宏、佐藤健一、十重田裕一 編 |
| 第5巻(5) | 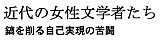 | 渡辺澄子、阿木津英、岩淵宏子、尾形明子、吉川豊子 編 |
| 第6巻(1) | 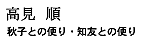 | 保昌正夫、竹内栄美子、十重田裕一、宮内淳子 編 |
| 第7巻(4) | 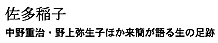 | 長谷川啓、北川秋雄、小林裕子、中野武彦、満田郁夫 編 |
| 別巻1(8) | 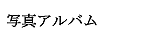 | |
*3ヵ月に1回配本・()付き数字は配本順
●A5判・上製カバー装・本文約300頁・予価6,090円(税別)
日本近代文学館資料叢書[第1期]
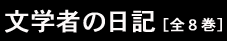 好評刊行中。いよいよ完結!
日本近代文学館編 好評刊行中。いよいよ完結!
日本近代文学館編
日本近代文学館は創立されて41年、現在の駒場に開館して36年
になる。その間蒐集された肉筆資料のうち文学者の日記類を翻刻出
版。いずれも初めて公刊される極めて貴重な資料ばかりで、その意
義は深く、文学・歴史の研究にも資するところが大きい。

各巻 税込価格 5,250円
A5判・上製貼函入り・本文200〜350頁
第1巻、第2巻、第3巻
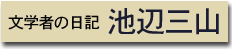
大沼敏男・富永健一・中丸宣明 翻刻・解説
池辺三山
本名吉太郎、名乗重遠。新聞記者。元治元〜明治45
(1864〜1912)
【第1巻】池辺三山(一)
熊本生まれ。幼児より漢学を学び、上京して同人社、
慶應義塾に学ぶ。初め政治家を志すが、『山梨日日
新聞』の客員として論説を執筆することで、ジャー
ナリズムの道に入る。東海散士の推挽で『経世評論』
の編集を経、『日本』に寄稿するようになる。細川
家世子の補導役を委嘱されて渡仏、4年間滞欧。
本巻は、渡仏以前の三山の姿を伝える。
|  |
【第2巻】池辺三山(二)
黎明期のジャーナリズムと関わり始めた若き吉太郎は、郷里熊本の旧藩主細川家の世子
留学の補導役を委嘱されてパリに赴き、3年余を暮らすことになる。その間家へ書き送っ
た89通の書簡と世子に随行して各地を旅行した時の日記とで一巻を成す。時あたかも日
清戦争の時期に当り、それを報じる外国紙を読むことで後年の大ジャーナリスト三山の眼
力が養われたものと思われる。
【第3巻】池辺三山(三)
滞欧中「日本」紙に寄稿した「巴里通信」で文名を馳せた三山は、帰国後朝日新聞に迎え
られて主筆を勤める。三国干渉の後、高まりゆくナショナリズムの波の中で活躍するが、
開戦に向かって緊迫の度を加える日露交渉の推移を追いつつ書き留めた日記は、読む者を
リアルタイムで当時の情勢の渦中に巻き込まずにおかない。衝に当る有力政治家や軍人の
風貌が所々に描出されて印象深い。

第4巻
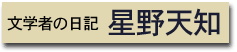
十川信介・下山嬢子・坂田純子 翻刻・解説
星野天知
評論家、小説家。
文久2〜昭和25年(1862〜1950)
江戸日本橋生。農科大卒。著書に『文学雑著破蓮集』
『山菅』『黙歩七十年』など。農科大在学中から明治
女学校に勤務、「文学界」(明治26・1〜31・1)
創刊同人、後年は文学から遠ざかり書道研究家。
収録する「自叙伝」は、幕末・明治初期から青年時代、
巖本善治、平田禿木、北村透谷、島崎藤村らのこと、
書道界、教育界まで多岐にわたる。
| 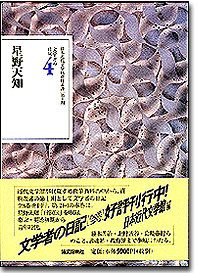 | |

第5巻
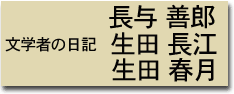
長与善郎
紅野敏郎・池内輝雄・田中栄一 翻刻・解説
生田長江・生田春月
曽根博義 翻刻・解説
第5巻は明治の青春日記とも言えるもので、善郎・
明治44年、春月・明治42年、長江・明治42年の
日記を収録する。
| 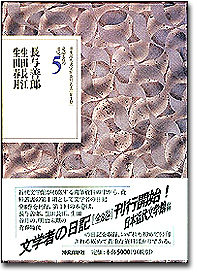
|
長与善郎
小説家、劇作家、評論家。明治21〜昭和36(1888〜1961)
東京生。東大英文科中退。著書に『項羽と劉邦』『青銅の基督』『竹沢先生と云ふ人』
『わが心の遍歴』など。日記は「侃孤独語集」と題された明治44年1月から5月のも
の。この年3月に学習院高等科を卒業、4月に前年創刊された「白樺」同人、1月には
大逆事件の死刑判決が出ている。
生田春月
詩人。明治25〜昭和5(1892〜1930)
鳥取県生。明治42年9月〜10月の日記を、師・生田長江の同年8月の日記とともに
収録。

第6巻、第7巻
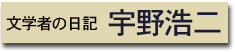
保昌正夫・柳沢孝子・田澤基久 翻刻・解説
第6巻・7巻の本巻は、文学の鬼といわれた
宇野浩二が精神を病んで癒え、再起に向かう
昭和5・7年の日記。 | |
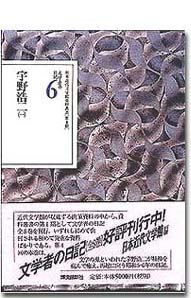 |
宇野浩二
小説家。明治24〜昭和36(1891〜1961)
福岡市生。幼時に大阪に移る。早大英文科中退。著書に『蔵の中』『苦の世界』『枯木の
ある風景』『芥川龍之介』『宇野浩二全集』全12巻など。昭和2年に続いて4年に再度
の大患に見舞われ、小説執筆を中断、「改造」8年1月号に「枯木のある風景」を発表し
て文壇に復帰する。収録する日記は、この時期に当たる昭和5〜7年。

第8巻
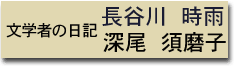
長谷川時雨 池内輝雄・森下真理 翻刻・解説
深尾須磨子 曽根博義・佐藤健一・藤本寿彦 翻刻・解説
|
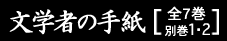
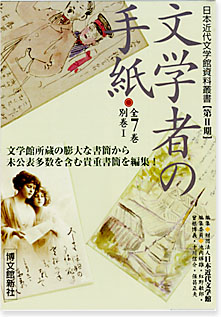
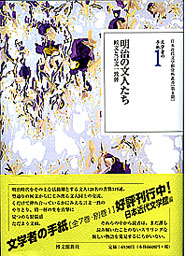

 A5判・上製カバー装 定価 6,930円(税込)
A5判・上製カバー装 定価 6,930円(税込)











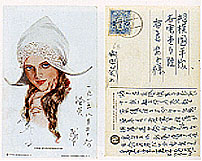


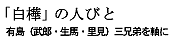
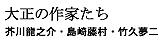

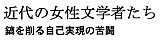
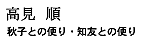
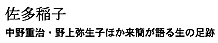
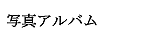
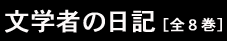 好評刊行中。いよいよ完結!
日本近代文学館編
好評刊行中。いよいよ完結!
日本近代文学館編